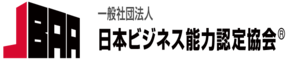【外国人労働者のメリット】入管法を理解して人手不足解消へ

厚生労働省の発表によると、日本における外国人労働者の数は2024年10月時点で、2,302,587人となっており、前年同期と比べると12.4%増加しています。[注1]
このように増加傾向にある外国人労働者は、雇用することでさまざまなメリットが生まれます。
今回は外国人を雇用することで生まれるメリットとその注意点を解説します。
[注1]「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末現在)
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html
外国人を雇用する最大のメリットは労働力の確保
外国人労働者を雇用する最大のメリットは、労働力を確保できるというところにあります。
日本において、労働の担い手である15〜64歳の生産年齢人口は、ピークであった1995年の8,726万人を境に減少しており、2065年には4,529万人まで減少するとされています。[注2]
[注2]国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口(令和5年推計)
pp2023_ReportALLc.pdf (ipss.go.jp)
このように、少子高齢化による労働力減少が進む日本においては、外国人を雇用することで、労働力の確保が期待できます。
グローバルな視点も備えられる
外国人を雇用することで、労働力確保が期待できるだけでなく、グローバルな視点が備えられるということが挙げられます。
ITをはじめとしたデジタル技術の発展は、グローバリズムを加速させています。
世界経済フォーラム(WEF)が発表している、各国の国際競争力を順位付けした「The Global Competitiveness Report 2020」[注3] では、日本は6位に位置づけられており、前年の5位からは順位を落としています。
この変化はわずかに見えるかもしれませんが、世界の経済変革やCOVID-19の影響、そしてイノベーション競争が激化する中で、日本がどう対応し続けるかが注目されています。外国人労働者の雇用が、企業にグローバルな視点をもたらし、競争力強化につながることが言及されています。
[注3] The Global Competitiveness Report 2020
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf
外国人を雇用する際に注意すべきポイント

外国人労働者の雇用はさまざまなメリット生む一方で、注意すべき点もいくつかあります。
1.在留資格の確認
外国人を雇用する場合、まずは在留資格を確認しましょう。採用対象となる外国人が在留資格を持っていても、期限が切れてしまっている場合はオーバーステイとして入管法に違反してしまうため、注意しましょう。
在留資格は次のように27の種類があります。
【在留資格に定められた範囲での就労が可能】
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転筋、興行、技能、特定活動
【就労が認められない】
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
【就労の制限がない】
永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者
在留資格は、在留カード、もしくはパスポートや就労資格証明書で確認できます。

外国人を正社員で雇う際に必要なビザと手続きの流れ
基本的に外国人は就労ビザを取得していなければ雇用できません。
今回は、トラブルを防ぐためにも、会社の経営者や人事担当の方が知っておくべき就労ビザの種類や取得条件などについて見ていきましょう。
2.雇用の手続きを確認しておく
外国人を雇用する場合、日本人とは異なる書類を届け出なければならないケースがあります。
まず、外国人労働者が雇用保険の対象となる場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。この際、備考欄には、在留資格、在留期間、国籍・地域、資格外活動許可の有無と記載する必要があります。
一方、雇用保険の対象とならない場合には、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します。

【外国人が日本で働くには?】雇用手続きや注意点を徹底解説
外国人労働者の雇用手続きを怠ると、懲役もしくは罰金が科せられることも。そこで今回は、外国人労働者の雇用手続きの注意点を紹介します。
3.労働条件を周知・理解してもらう
日本で就労する外国人の全員が、日本語に堪能なわけではありません。場合によっては、会話は問題なくできていても、読み書きが苦手という外国人もいるでしょう。
そのような外国人に対して、採用後の労働条件を周知して理解してもらうために、外国語で作成した労働条件通知書を準備しておきましょう。入社後、双方の食い違いによるトラブル防止につながります。

【外国人が日本で働くには?】雇用手続きや注意点を徹底解説
外国人労働者の雇用手続きを怠ると、懲役もしくは罰金が科せられることも。そこで今回は、外国人労働者の雇用手続きの注意点を紹介します。
4.日本特有の慣例を理解してもらう
日本と外国では文化の違いがあるため、日本特有の慣例を理解してもらうようにしましょう。
たとえば、長期雇用や年功序列といったことは、就労を続けるうえで理解しておいてもらう必要があります。

【日本語能力試験N1・N2なら安心?】日本で働く外国人に教える際の注意点
日本語能力試験N1・N2だからといって、日本人と同じように仕事ができるとは限りません。今回は、外国人労働者が働きやすく、スムーズにビジネスシーンに対応できるようにするための指導法を紹介します。

入社試験や昇進試験に活用も!
日本の文化やビジネスマナーを理解していただくことを目的として実施しています。習熟度に応じて階級が分けられているので、どの程度のビジネス能力を有しているか判別が可能です。
5.入社後のフォロー体制を築いておく
外国人労働者を受け入れた際は、外国人労働者がストレスを感じないような環境づくりを心がけましょう。
定期的なヒアリングや日本語の教育といった、よりスムーズに仕事を進めるために必要なフォロー体制を築いておきましょう。
外国人向け実務能力研修で日本の仕事を理解してもらう
日本のビジネスマナーは、海外と異なる点がいくつもあります。
そのため、外国人労働者には業務を円滑に進めるために、年功序列、名刺交換の方法、お辞儀や礼儀作法といったような日本独自のマナーを理解してもらわなければなりません。
このようなビジネスマナーの講習を社内で行ってしまうと、担当する従業員がコア業務に集中できないといったデメリットが発生してしまいます。そのため、専門機関での研修を活用するのがおすすめです。

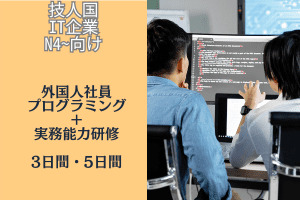
外国人雇用で生まれるメリットを最大限に引き出そう
外国人労働者を雇用することで、労働力の確保、グローバルな視点といったメリットが、企業に生まれます。ですが、このメリットを生み出すには、受け入れ体制の強化といった注意点をしっかりと押さえておく必要があります。
特に、日本特有のビジネスマナーに関しては、自社の社員をコア業務に集中させるためにも、ビジネスマナー講座を活用しましょう。
この記事を書いた人

日本ビジネス能力認定協会理事 佐々木敦也
アメリカ駐在を経て、1991年にソフトウェア会社を設立。代表取締役として会社を経営する傍ら、外国籍社員の採用・育成を行う中での経験を教材にまとめ、2015年に日本ビジネス能力認定協会を設立した。
著書:『外国人実務能力検定公式テキスト』